「自分自身に希望を持つこと」は、「旗を立てることだ」。
そんな信念の基に生まれたプロジェクト「ぼくたちはどこに旗を立てよう」。
「人」というものへの興味が尽きないシングメディア佐藤が自分自身の旗を立て続ける人たちと語り合っていきます。
第四回となる今回からは、新シリーズ「BABEL LABEL(バベルレーベル)篇」をお送りしてきます。
旗立人は日本大学芸術学部在学中に自主映画を作っていた同世代の仲間を中心に結成された映像ディレクター集団/映像制作会社、株式会社BABEL LABEL(バベルレーベル)の代表の山田久人さん、さらに、設立者である映画監督の藤井道人さんです。
先日発表された第43回日本アカデミー賞では、優秀作品賞・優秀監督賞をはじめ、6部門受賞した映画『新聞記者』。
昨今の政治的題材に取り組みながら、大きな情勢に翻弄され苦悩する個人に光を当てた人間ドラマを作り上げ、劇場では満席が相次ぎ、終演で拍手が起こるという所謂「新聞記者現象」を引き起こしました。
Vol.4では、そんな話題作を手がける藤井さん、さらにそれを支える山田さんの過去のお話、ルーツについて詳しくお伺いしました。

今回のセクションはこんな感じ。
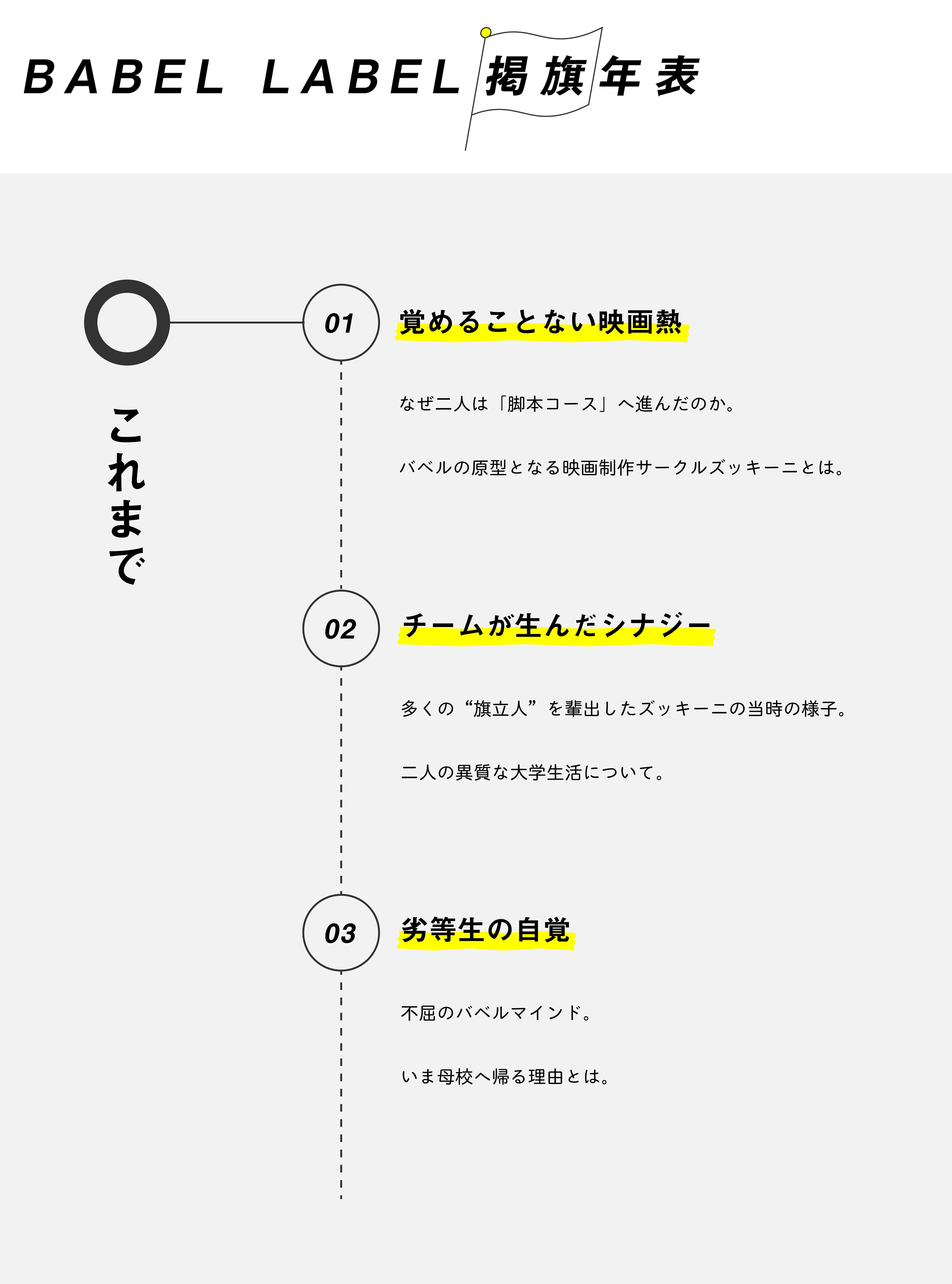

映画やCM、MVなど様々なジャンルの映像を手がける株式会社BABEL LABEL(バベルレーベル)代表、プロデューサー。
株式会社AOI Pro.退社後、そこで培った経験を生かし、代表として様々なディレクターが所属するBABEL LABELの基盤を担う。
大学時代の映画制作がきっかけで映像の道へ進む。

株式会社BABEL LABEL所属の映画監督・脚本家。
2010年にBABEL LABELを設立。
2014年伊坂幸太郎原作映画『オー!ファーザー』でデビュー。
2019年公開の映画『新聞記者』では第43回日本アカデミー賞6部門受賞、第32回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞、2020エランドール賞、第29回映画祭TAMA CINEMA FORUM 第11回TAMA映画賞を受賞。

藤井道人が掲げた旗
佐藤一樹(以下佐藤)ーーでは、さっそくですが、インタビューを始めて行こうかなと思います。年末(このインタビューは2019年12月末に行われたものです。)ということで、ざっくり、2019年はどんな年だったでしょうか。
山田久人(以下山田) 藤井さんはいろいろあったんじゃないですか。
藤井道人(以下藤井) そうですね、2019年を一言で言うならハーベストといった感じでしょうか。10年やってきたことをこの1年で収穫したというか。だからまた種を植えます。次の1年は。
佐藤ーーその種まきはいつ頃からやっていたんですか?
藤井 それはバベルを創ってからずっとですね。この10年間でやってきたことが2019年に一気にどっと収穫できたというか。
佐藤ーー確かにその印象は強いように思います。
藤井 狙っていたわけじゃないんですけどね。全部が偶然というか。経営者のコラムとかでよく「まずはこれをするのがいい」といったHow toみたいなものがあったりするじゃないですか。僕はそういうものが全くなくて(笑)。本当に全部が偶然なんですよね。

佐藤ーーBABEL LABELが設立10年目を迎えたということですが……。
藤井 名乗り始めてからざっくり10年目ですね。確か2009年頃から名乗っていたんですが、組織化してクレジット化し始めたのが2010年頃だと思います。その頃に自分でロゴも作りました。会社にしてからは7、6年くらいかなと思います。

佐藤ーーこのインタビューは3部構成でいこうと思っていまして、第1部は過去篇ということで、それぞれプロデューサーと監督というところでそこを目指したきっかけ、経緯、その辺をお聞きしていこうかなと思います。ではさっそく藤井さんから。
藤井 僕らは二人とも大学時代、脚本コースというところで、脚本を専攻していたんですけど二人とも本当に不真面目な学生で、大学にはろくすっぽ行ってなかったですね。そんな中で自分たちの救いだったのが、サークル活動でした。脚本コースって映画を作る権利は与えられていないので、自分たちで作るしかなかったんですよね。それで、僕たちが入る前は佐藤隆太さんとかがいた「ズッキーニ」っていう映画制作サークルがあるんですけど、2人でそこに入りました。僕たちが入った時は5人くらいしかいないサークルでした。
そこで18歳くらいから映画を作っていたんですけど、その時は何者になりたいとか監督になりたいとかは一切思っていなくて、ただただ楽しかったですね。単純に。今もそうなんですけどね。映画作りが楽しいってだけでそのまま正直15年くらい経ったっていうだけなんです。
脚本家志望で監督もやり始めたんですが、監督をするタイミングが増えてきて、脚本だけやるってことが無くなって、気づけば監督をメインでやっていました。もともと監督志望ではないんです。
佐藤ーー大学ではなぜ脚本コースに入ったんですか?
藤井 それはやっぱり脚本が好きだったんですよね。それこそ山ちゃん(山田)は好きな脚本家がいて、僕も当時は *クドカン(宮藤 官九郎)さんとかあとミシェル・ゴンドリーの脚本家の*チャーリー・カウフマンが好きだったので、単純に脚本の勉強がしたいなって思っていましたね。
佐藤ーーたとえ多少の興味を持ったとしてもなかなか勇気のいる選択だとは思うのですが……。
藤井 でも普通の大学に行く方がきっと大変だと思います。センター試験って5科目ぐらい勉強しないとだめじゃないですか。僕はほとんど勉強ができなかったんですよね。そんな中でも英語は一応帰国子女なのでできる、国語は普段使ってる言葉だからできる、日本大学芸術学部はこの2科目で受験できたんですよ。だから理科・社会とかはほとんど勉強したことがないです(笑)。この2科目で受験できたっていうのが日芸(二人が通っていた日本大学芸術学部)を選んだ理由としては一番大きかったんじゃないかと思います。
佐藤ーー山田さんはなぜ脚本コースに入ったんですか?
山田 僕はもともとすごいテレビっ子で。*野沢尚という脚本家がすごく好きなのですが、その人が日芸の出身なんですよね。中学の時通学の時間が長くて、その時間にずっと脚本を読んでいました。ドラマが好きで見ていたから小説より脚本の方が面白いなと思って。それで、脚本を書きたいと思った時に、日大の付属の中学に通っていたので、日芸に行けばいいんだと思ったんですよね。
日芸に行ってからは、藤井が言うように脚本コースに所属して映画制作サークルに入りました。兄の結婚式で中国に行って、帰ってきたら藤井が「山ちゃん、もうサークル決めといたよ」って。きれいなお姉さんに勧誘されたらしくて「その映像サークルに入ることにしたから」って。「ああわかった」って言って、それでズッキーニ入ることになって、代表・副代表をやりました。今思うとそれがまぁ「バベル作ったから」っていうことだったんだと思います。藤井は、行く方針を決めて旗を立ててくれたんですよね。リードする立ち回りだなと最近でもよく思いますね。

*チャーリー・カウフマン:アメリカの脚本家・映画プロデューサー・映画監督。で英国アカデミー賞脚本賞、アカデミー脚本賞を受賞。
*野沢尚:日本の脚本家・推理小説家。代表作に「眠れる森」「結婚前夜」がある。

お金よりも大切なもの
佐藤ーー藤井さんははぜ山田さんをズッキーニに誘ったんですか?
藤井 だって一人で入りたくないから(笑)。
一同 (笑)。
藤井 本当に人数が少なかったんですけど、でもすごく可愛いお姉さんから「一緒に映画作りませんか」って言われたら「これが大学か」と舞い上がるじゃないですか(笑)。18歳まで剣道しかやってこなかったからあまり学校生活みたいなものに期待は持っていなかったんですけれど、これは楽しそうだなと思って。それで数人の仲間を誘って入ったんです。その時は先輩方に本当にお世話になりました。編集するために家を貸してくれたりとかして。そんな先輩方に恵まれたということもあって、本当にサークル活動はすごく楽しかったですね。

佐藤ーーサークルとしては最初はあまり大きくなかったんでしょうか?
藤井 そうですね。だからと言ってはあれですが、変な責任感もなくのびのびと活動できて、僕たちが入った当初は、僕たちも含めてやっと10人くらいだったんですけど、卒業する時は200人くらいまで増えていました。めちゃくちゃ増えました。
佐藤ーーなぜそれほどメンバーを増やすことができたのでしょうか?
藤井 きっかけは多分僕たちが三年生の時だと思います。二年生の時はやり方もちゃんと分からない状態でむちゃくちゃに映画を撮っていました。照明やマイクもない様なところで2年くらいやっていて、でも、三年生の春先頃に学内の小さなコンペでグランプリをとったんですよ。それで、ちょっと大学生離れしたフォルムの二人が代表副代表をやっているサークル、という印象がついて、その二人で*「机出し」というか「いっぱい若い子たち入れよう」と勧誘して、それでみんなが入ってきてくれました。
それから僕たちが四年生になった時、「学生で初めて映画を撮る時って何をやっていいかわからない」っていうことがわかっていたので、ワークショップ的なことをやろうという話になりました。どういう風に作ればいいかとか、こんな部署があるよとかそういうことを話す場を設けるということをやったらすごくメンバーが増えたんですよね。
佐藤ーー*山田智和さんや、カメラマンの*今村圭佑さんなど、ズッキーニのメンバーは今いろんなところですごく活躍していますよね。それぞれがチカラをつけてきている感というか。
藤井 そうなんですよ。みんな活躍しているんですよね。頑張っている人がいっぱいいますね。
佐藤ーーなぜみんなそんな風に活躍できているのでしょうか?
藤井 時代みたいなものもあると思っています。結局冷え込む時代ってみんなの熱量が低いから「俺やんなくていいや」とかふわっとしているんですけれど、僕たちはみんながみんな切磋琢磨していたんですよね。「あいつが撮ったから次は俺が撮る」「あいつのやり方には納得いかない、だから俺はこうやる」とか。後輩からは「藤井さんたちを超えたい」みたいなことを言われていました。それで彼らは彼らでチームを創って、すごく素晴らしい作品を世に出していっている。やっぱり相乗効果だと思うんですよ。下の台にはまた*川島(川島直人)って監督がいて、彼も商業デビューしているし、僕たちが何かしたというよりはみんなが勝手に作用していったと言う感じで。それは僕としてはすごく嬉しいことだと思っています。
佐藤ーー山田さんと藤井さんは一緒に映画を作っていたんですか?
山田 なんか同じズッキーニの中でも藤井班と山田班があったんですよね。やっぱりそれは今もそうだし、大事な時には一緒にやりますが、まあそれぞれはそれぞれで、というか。
藤井 できるやつとか可愛い子は大体山田班にいましたね。
一同 (笑)。
藤井 こっちはもうなんか成れの果てみたいなチームでした(笑)。
佐藤ーーじゃあそれぞれがそれぞれでチームというか、徒党を組んでいたんですね。
藤井 そうですね。班っていうものがあって、それが僕たちの時代には二つしかありませんでしたが、下の代になったら四つになって、またそれが八つになってというように細胞分裂していきました。
佐藤ーーお互いを意識し合っていた?
藤井 僕たち自体は一緒に仕事をしていたので、そんなにバチバチしていたわけではないです。ダンスやイベント関係のカルチャーDVDみたいなものの監督とかを一緒にやったりしていました。あと山ちゃんは山ちゃんで別で監督とか演出部を学生時代からやっていましたね。

佐藤ーーそれは普通にお金がもらえるような感じのものですか?
山田 それが、そんなにお金がもらえるものではなくて。ある時、芸人さんが100本映画を作るみたいなものの助監督をやったんですけど、人がいなかったので、本当なら自分はサードでもフォースでもないのかもしれないところを、二人しかいないので勝手にセカンドになるみたいな感じでしたね。全くやり方もわからないのに(笑)。これは今も変わりませんがお金より経験の方がずっと大事だなって思っています。映像をやっていて「よっしゃ儲かった」っていうのはないですね。
大学在学中はお金はもちろんなかったですが、授業にも行っていなかったですね。大学に大きな校庭みたいな場所があるんですけど、そこでゴムボールと棒で二人で野球をやっていましたね。
藤井 軟式ボールとバットじゃないんですよ。カラーボールと木の棒でした。なぜかって言うと変化球がすごく曲がるからおもしろくて(笑)。そしたら日芸の2チャンネルに「あいつらなんなの」とか書き込まれていたらしくて(笑)。
山田 だってそんなやつらいなかったですから(笑)。大学ってもっときれいな格好して、いろいろみんな夢とか語っているのに、僕らは本気でボールの曲がり方とかを考えていました。あれでちょっと野球が上手くなりましたね(笑)。

佐藤ーー本当にあまり授業に出ることなく遊んでいたんですね(笑)。
藤井 今だからわかりますが、すごく意味のあることを先生たちは教えてくれていたと思います。ただ、18歳の、まだアプリケーションがないというかベーシックになってない人たちに教えるには非常に固かったというか。それよりは大学っていう全国からいろんな人たちが集まってきて価値観とかが違って、ある種高校の教育とも違うあの環境で、みんな映画が好きっていうあのコミュニティに集まった時の高揚感が優ったというだけなんですよね。彼らと一緒にいてお酒を飲んで失敗ばかりを繰り返す方がまあ非常に意味があったのかなと思います。でも今は後悔もしていますよ。もうちょっと映画を見ておけばよかったなとか。
佐藤ーー当時はこんな風に遊んでいる方が意味があると思っていたわけではなくて、ただ楽しいから遊んでいたんですかね?
藤井 思っていなかったですね(笑)。ただ、だらしないなと思っていました(笑)。自覚はしつつ楽しいの優先というか、まぁ用は社会人でもないし思いっきり楽しもうと言う感じで。

*山田智和:CAVIAR所属の映像作家・映画監督・写真家。クリエイティヴチーム「Tokyo Film」主宰。SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2019において、「BEST VIDEO DIRECTOR」を受賞。日本大学芸術学部映画学科映像コース卒業。
*今村圭佑:カメラマン、撮影技師、撮影監督。『デイアンドナイト』(2019年)『新聞記者』(2019年)など藤井監督作品にも携わる。日本大学芸術学部卒業。
*川島直人:Guns Rock Inc.所属の映画監督。

学習者というスタンドポイント
佐藤ーー映画というものの存在はやはり大きいですね。
藤井 そうですね、誰に頼まれてやっていた訳ではなく、ただただやりたくてやっていました。
山田 大学生時代はすごく楽しかったです。自分たちが楽しいと思うことをずっとやっていました。
日芸は芸術っていうことに対して好きなことをやっている人たちが多いんですよね。で、ちょっとしたモラトリアムを感じていた時期でもあって。だからしばらくはそこの猶予期間を楽しむことを優先してて、どこかのタイミングでそれを仕事にできるように頑張れたっていうのはあるのかもしれないですね。
佐藤ーー日芸自体がやりたいことをやろうとしている集団だから、いわゆる普通の四年生大学とは違うんですね。話を聞いていると、みんな虎視眈々としているように思いました。群れることを嫌うというか。その中でもやはり淘汰されていく人もいるんでしょうか?
藤井 そうですね。逆に言うと、この業界でやっていくっていう人はあまり多くないかもしれません。制作会社とかに就職するっていうのは聞きますが、監督をやっているっていう人は同期だといないですね。大学を卒業した後、どこに誰が就職しましたみたいなものを見た時、パン屋に就職した子とかもいましたね。
佐藤ーーそんな中、自分たちは優れているっていう感覚みたいなものはあったんでしょうか?
藤井 劣等生だっていう自覚はありました。僕たちって監督コースでもないから、どちらかというと見下されていたんですよね。
佐藤ーー監督コースは割とスター性があるという感じなんですかね。
藤井 そうですね、花形です。だから*志真くん(BABEL LABEL Dir志真健太郎)がちょっと俺たちいけてるぜオーラを出してくるんですよ。で、僕たちみたいな素行の悪そうな若者はすごく下に見られたっていうのは覚えています。
大学で僕がフリーランスになると決めた時も一緒に映画を作って、カメラをやってくれていた女の子に「絶対藤井ちゃん成功しないと思う」って普通に言われたんですよ。そういうの結構燃えるタイプで。「俺もそう思う」とか言いながら笑っておいて内心ではすごいグツグツしていましたね。

山田 それで言うと最近、日芸の先生に藤井が呼んでもらって、大学の頃そんなにコンタクトをとっていなかったような人たちとしっかり映画の話をしているのを見てると、藤井が就職しないで映画を作って、それで映画監督として映画学科の先生たちが認めてくれているっていうのはすごいいい話だなって思いますね。
佐藤ーーそれはやっぱり還元しようというか、まあ具体的にはどのようなマインドで臨んでいるのでしょうか?
藤井 やっぱりお世話になったと思うんですよね。あとは全部に通ずることなんですが、大学のために行っているというよりは自分のためというか。自分が今どこの立ち位置にいてっていうのがブレないようにちゃんと母校に戻ってここで思っていたことや感じていたことを思い返さないと”浮く”んですよね、宙に。自分が何者かになった気分になってしまうので、それを戒める意味でも母校に帰ったり、若い学生さんたちと話したりします。そうすると、自分はこの場所から今ここにいるんだなっていうのが線になりやすい。だから自分のいる立ち位置っていうのを再確認するための仕事だと思って行くことが多いですね。

佐藤ーーそんな風に帰ることで、自分の立場を再確認できる、ということに気づいたのはいつ頃ですか?
藤井 あまり明確にいつだなっていうのはないですね。徐々にだと思います。高校や中学にも行くんですが、高校生とか中学生にどういう風に監督になったかっていうのを話していると全然話を聞かない子とかがいて「俺こうだったんだよな」っていう風に思うと同時に、でもそれでいいなって思うんです。「なんで俺の話を聞かないんだ」じゃなくて「聞かないよね人の話なんて」って思うので。でも例えば「RADWIMPSが…」とかこっちがその子たちが聞きたいことを言ったりすると、ピクッとなるんですよね。そこをちゃんと見てあげるためにも自分の勉強として行っていますね。
佐藤ーー「教える」という立場ではなく、自分も学びに行くという姿勢を大事にしているんですね。
藤井 「教える」となるとちゃんとお金をもらって、その費用対効果で何が生まれたかっていうのをレポートにして、そこまでが仕事だなっていう風になる。僕はそれはやだなって思うんですよね。だからそういうのって絶対にお金はもらわないですね。演技のワークショップとかもそうなんですが、「教えちゃう」とやっぱりお金を取らなきゃいけないっていう風になるというか、そういう立場ではないと思っているので。
佐藤ーー藤井さんは結構自分を戒めるタイプなんですね。
藤井 失敗するのが怖いんですよね。ミスが怖い。ミスって嘘と似ていて、一個ミスをすると雪だるま式に全部ミスになるじゃないですか。だったら、嘘なんかつかなきゃいい、ミスなんてしなきゃいいんですけど、ミスなんてしないっていうのは難しいんですよね。ミスをしないために自分が結構無敵なコンディションでいないとそのミスにちゃんと謝れないというか。だから疲れたりしないようにしようと思っていて。二時間しか寝ていなくて三日間みたいなことは最近はもうやらないようにしています。判断能力が鈍るので。でも未だにそういうことで年一ぐらいで怒られるんですよね(山田さんに)。怒られるの嫌いなんですよ(笑)。だから怒られないようにしていますね。
佐藤ーーなんか「まだまだ感」というか。そういうマインドをひしひしと感じます。
山田 全然まだまだですよ。今回もこうやって取材してもらっていますが、そんな取材されるようなものでもないと思ってますし(笑)。でも今回は初めて藤井ちゃんと一緒にってことだったのでせっかくなので、受けさせていただきました。

#ぼく旗 編集後記
大学生というのは、猶予期間である様に見えて、案外「学生」というものや「年齢」というものに囚われているといったかなり特殊な時間であるように思う。
人生の中の制限がない様である特別な時間。そんな時間を無我夢中で映画作りに費やした藤井さんと山田さん。
今回お二人からお聞きしたエピソードは非常に血と汗が感じられるものだった。
ただただ自分の好きなものに向かって走る、そんな素敵な青春時代を私も送りたかったと、少しだけ羨ましく感じてしまった。
お二人から「今もまだ突っ走っている途中だ」という強い想いがひしひしと感じられたのが非常に印象的だった。
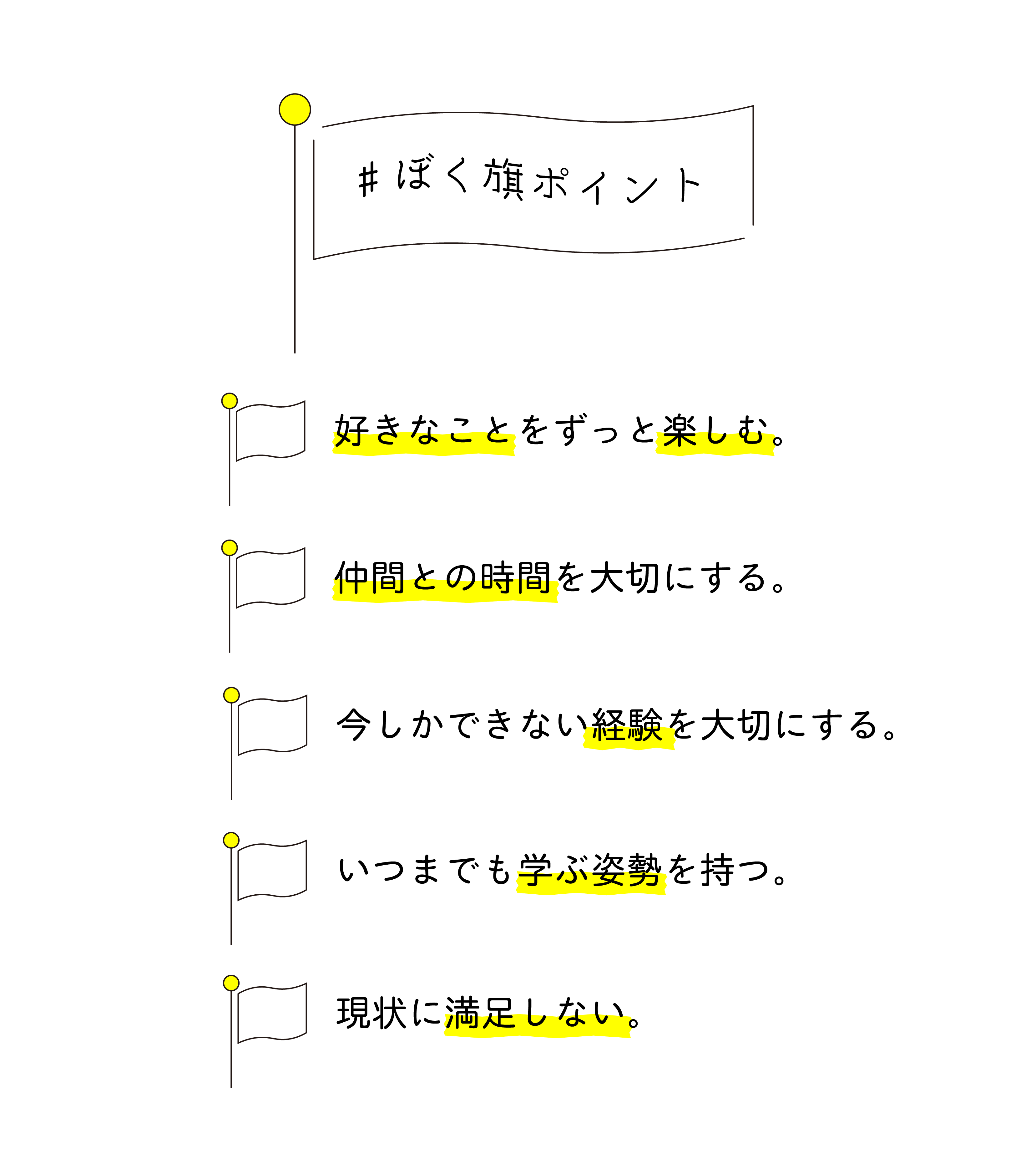

株式会社ダダビのPR。クリームソーダとロックがすき。パンクに生きたい。現在シングメディアで修行中。
